-

-
注連飾り
2024/1/3
「注連飾り」日本独特の飾り物です。 自宅の玄関などにも飾りますが、神社の注連縄は力強く、神聖で清浄さを感じます。 注連縄は神の領域と俗世間との境界を示し、穢れが入るのを禁じています。 稲わらは真夏のま ...
-

-
高砂
2024/1/3
高砂とは、高砂の松と住吉の松、二本の松を人格化して夫婦愛と長寿を願うことです。 これは、能の「高砂」からとった言葉です。阿蘇の神主が都に上る途中、播磨の高砂の浦に立ち寄る。熊手と杉箒を手に松の下の木陰 ...
-

-
萬歳(まんざい)
2024/1/3
「萬歳」とは、新年の言祝ぎの話芸として全国で興り、現在の漫才の元となったものです。 扇子を持つ太夫(たゆう)と小鼓を持つ才蔵(さいぞう)の二人一組が基本です。二人でかけ合いをしながら祝い言葉を唱えて家 ...
-

-
麒麟の茶碗
2024/1/3
我が家にある麒麟の九谷焼の茶碗。 麒麟とは、頭が狼で体が鹿。尻尾が牛で足が馬。一角を持つ架空の動物です。 中国から伝わる四神とは、東の青龍、西の白虎、北の玄武と南の朱雀であるが、これに中央の麒麟も入れ ...
-

-
絵馬
2024/4/20 ema
実家の神社には、馬小屋があって大きな白い馬の人形が置いてあって、小さい頃に何だか怖いなぁと思っておりました。 そして、この絵馬。馬が白馬の時と黒い馬の時があるなと思っていました。調べてみると白と黒では ...
-
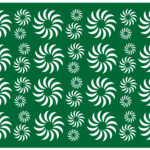
-
獅子文様
2022/10/21
「獅子」とは、ライオンを文様化されたものと言われ、中国経由で日本に伝わりました。ライオンを知らない日本人は、中国風の架空の動物として受け入れ、邪気を払う獅子舞として主に伝わりました。 獅子舞は、お正月 ...
-

-
梅の文様
2023/3/1
寒い時に咲く梅は不老長寿を意味しています。そして、花びらが五弁あることから、福・禄・寿・喜・財の五福を表してると言い伝えられています。 奈良時代の頃の花見と言ったら、桜より梅をさしていました。そんな古 ...
-

-
松の文様
2022/8/26
常緑樹の松は、長寿の象徴である。老松には、龍が住むと考えられていました。 「松」の漢字を分解すると「八ムの木」=「八白の木」となる。「八白」は艮(うしとら)のこと。艮の方角は、天地の陰気の終わりと陽気 ...
-

-
ぶりぶり
2025/3/17
「ぶりぶり」という香合があります。これは、昔「振振毬杖(ぶりぶりぎっちょう)」という八角形の木槌に車輪と紐のついた男の子の遊び道具でした。 「ぶりぶりぎっちょう」と掛け声をして紐を引っ張って、輪のよう ...
-

-
お節料理
2022/1/7
お正月のお節料理。年の初めに食べる料理ですが、一つ一つに大切な意味が込められています。みなさんは何がお好きですか。 一、紅白かまぼこ 紅白はおめでたい席には欠かせない色。白は ...
-

-
寒餅
2023/2/24
寒稽古の後の「ぜんざい」。 武道を習っていた時には、必ず用意していましたが、なぜ「ぜんざい」を頂くのか。 「ぜんざい」は寒餅と小豆から作ります。 「寒餅」は、小寒から大寒の間についたお餅のことで、この ...
-

-
七草がゆ
2024/1/6
「七草」は五節句の一つであります。一月一日ではなく、一月七日「人日」が節句の一つになります。一月一日は鶏の日。二日は狗の日。三日は羊の日。四日は猪の日。六日は馬の日。七日は人の日とされています。それぞ ...
-

-
嶋台の由来
2023/1/21
「嶋台」とは、金銀の重なった赤楽茶碗のことです。金銀二段になっていて盃の形、蓬莱山を表しています。本歌は長入作になります。 高台は金の茶碗は五角形で鶴を表し、銀の茶碗は六角形で亀を表しています。おめで ...

